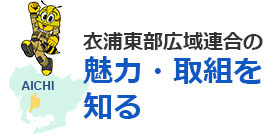ここから本文です。
住宅防火・防災キャンペーン【予防課】
更新日:2025年8月18日
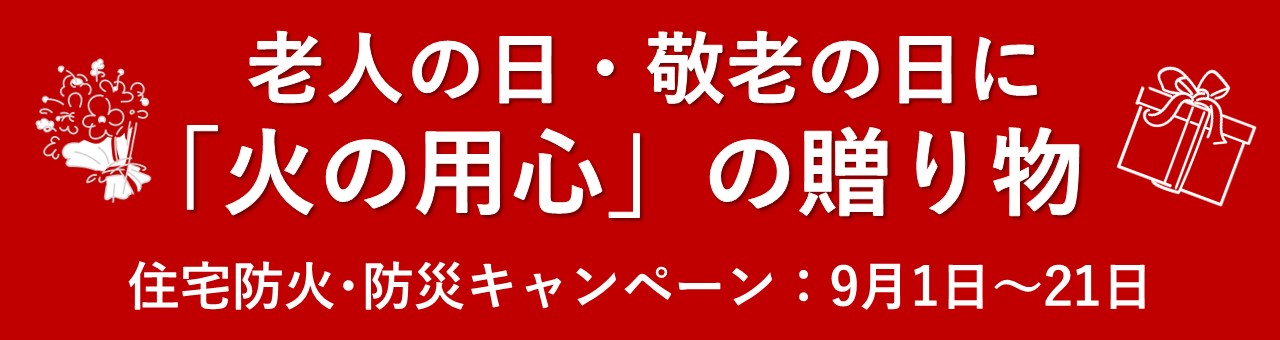
「火の用心」の贈り物を
近年、住宅火災における死者数は年間900人前後と高い水準で推移しており、そのうち7割以上が65歳以上の高齢者となっています。さらに、今後も高齢化の進展が予想されることから、高齢者の住宅火災対策はますます重要になっています。
消防庁では、住宅火災から高齢者を守ることを目的に、毎年9月1日から21日までの期間を「住宅防火・防災キャンペーン」と定め、「老人の日・敬老の日に『火の用心』の贈り物」をキャッチフレーズに掲げて、防火・防災対策の普及を図っています。
このキャンペーンは平成24年度から実施されており、高齢者に対する火災予防の注意喚起や、ご家族による「住宅用火災警報器」や「感震ブレーカー」「住宅用消火器」「防炎品」などの贈り物、さらには、設置済みの住宅用火災警報器の点検や交換を高齢者に代わりご家族が実施することなどを推進しています。
大切なおじいちゃんやおばあちゃんが火災の被害に遭わないよう、老人の日や敬老の日をきっかけに、身近な防火対策を考えてみませんか?
- 老人の日:9月15日(老人福祉法第5条)
- 敬老の日:9月の第3月曜日
高齢者を住宅火災から守る4つの備え
1.住宅用火災警報器の点検・交換

住宅火災で死者が発生する要因として、火災の発見が遅れ気づいた時には火が大きくなり、既に逃げ道がなかったと思われる事例が多く報告されています。
火災の発生を早く知り、被害を軽減するために、「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。設置から10年以上経過している場合は、電池切れや機器の劣化が懸念されるため、本体の交換が推奨されます。
正常に作動しているかを確認するために、年2回程度の定期的な点検を行い、設置後10年を目安に本体を交換しましょう。
2.感震ブレーカーで火災を防ぐ

大規模地震発生後、電気が復旧した際に、転倒・破損した家電製品に電気が流れることで通電火災が発生する可能性があります。これを防ぐには、「感震ブレーカー」の設置が有効です。感震ブレーカーは地震の揺れを感知し、自動的に電気を遮断する仕組みで、後付けも可能な簡易タイプも多く市販されています。木造住宅が多い地域や高齢者世帯に特におすすめです。
3.住宅用消火器で初期消火

火災が発生した際、初期の段階で火を消し止めることができれば、被害を最小限に抑えることができます。そのためには「住宅用消火器」の備えが重要です。近年では、小型で軽量なものや、スプレー式の簡易消火具など、高齢者でも扱いやすい製品が増えています。いざというときに「使えない」では意味がありません。日頃から使い方を確認し、すぐに手が届く場所に設置しておきましょう。
4.防炎品を使いましょう。

死者が発生した住宅火災で、最も多い出火原因は、たばこによるものです。なかでも寝たばこにより発生した火災で多くの死者が発生しています。
また、調理中に、コンロの火が衣服に燃え移ることにより亡くなる高齢者もいます。このような火災による死者を減らすため、枕や布団などの寝具、パジャマやエプロン等が燃えにくく作られた「防炎品」を使用することをお薦めしています。
最後に
「プレゼントに警報器を?」と、最初は驚かれるかもしれません。しかしそれは、安心を届ける何よりも実用的な贈り物です。今年の「老人の日」や「敬老の日」には、大切な方への“火の用心”の気持ちを込めて、住宅用火災警報器や防炎グッズ、感震ブレーカーなどの防火・防災グッズを贈ってみてはいかがでしょうか。それが、命を守る第一歩になるかもしれません。
住宅防火・防災キャンペーンは、9月1日から9月21日まで実施されます。ご家族や地域の皆様とともに、改めて火災への備えについて考える機会として、ぜひご活用ください。
関連リンク
お問い合わせ
消防局予防課
電話番号:0566-63-0136
ファクシミリ:0566-63-0130
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広報
- 春季火災予防運動【予防課】
- 火災が増えています!身の回りの確認を!【予防課】
- 消火栓付近での駐車禁止のお願い【消防課】
- 消防車や救急車の緊急通行時の安全確保にご協力を【消防課】
- リチウムイオン電池による火災防止月間【予防課】
- 秋季全国火災予防運動【予防課】
- [開催予告]もっと知ろうよ!きゅうQたい2025 in 大浜てらまちウォーキング【消防課】
- [開催予告]もっと知ろうよ!きゅうQたい2025 in 知立ドリームマルシェ【消防課】
- 住宅における地震火災対策【予防課】
- 全国消防救助技術大会出場【消防課】
- 119番の日【通信指令課】
- 全国消防救助技術大会出場決定報告【消防課】
- 「救急の日」及び「救急医療週間」【消防課】
- 住宅防火・防災キャンペーン【予防課】
- 電気器具等の安全な取扱い【予防課】
- マイナ救急実証事業の取り組み【消防課】
- 火遊び・花火による火災の防止【予防課】
- 危険物安全週間【予防課】
- 地震に対する日常のそなえ【消防課】
- 風水害に備える【消防課】